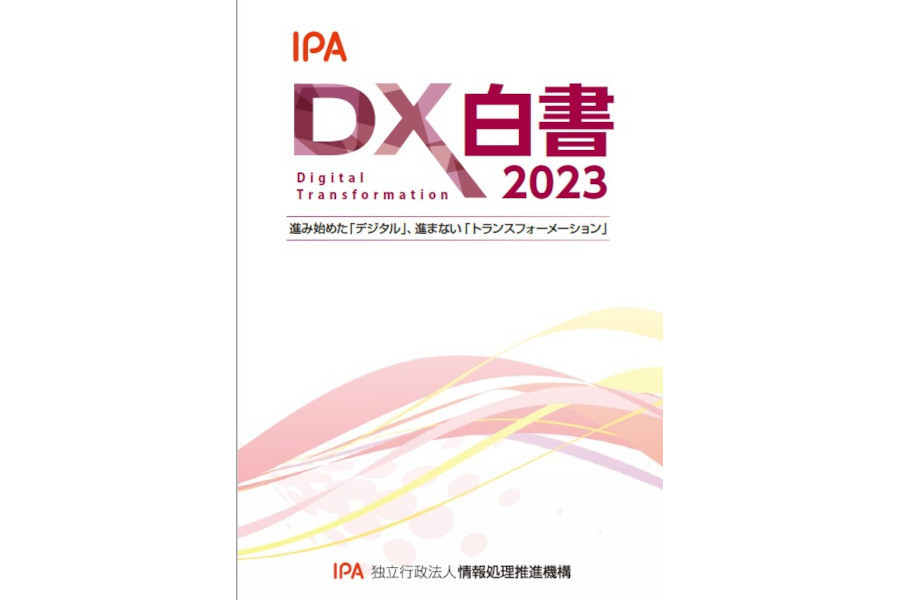独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が、「DX白書 2023」を発行した。日本におけるDXの推進状況のほか、人材育成やテクノロジーの進化など、IT産業全体の最新動向も捉えることができる内容となっている。日米企業に対するアンケート結果をもとにした比較も興味深い。今回の「DX白書 2023」の副題は「進み始めた『デジタル』、進まない『トランスフォーメーション』」であり、そこからも日本におけるDXの課題が提示されている。日本のDXについて、どんな現状が明らかにされたのか。
-
「DX白書 2023」。IPAのウェブサイトで、PDF版をダウンロードできる
IPAでは、2009年から「IT人材白書」、2017年から「AI白書」を発行し、IT人材や新技術の動向について情報を発信してきた。2021年にはDXの進展を捉えながら、両白書から人材と技術の要素を継承し、経営や戦略の視点を加えた新たな白書として「DX白書」を創刊。今回の「DX白書 2023」は、その第2弾となる。
IPA 社会基盤センター イノベーション推進部の古明地正俊部長は、「企業のDXを加速させるには、先端技術への理解や人材の獲得のみでなく、事業環境の変化に、迅速かつ柔軟に対応するために、経営のコミットメントが不可欠となる。IPAでは、戦略、人材、技術の面からDXを推進するための情報を総合的にカバーする白書を発刊する必要があると考えた。DX白書は、DXに取り組む企業にとって、具体的な手立てを探るための指南書になる」とした。
-
独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 社会基盤センター イノベーション推進部の古明地正俊部長
「DX白書 2023」では、DXへの取り組み事例の分析を踏まえて、日本におけるDXの取り組み状況を俯瞰するとともに、日米企業へのアンケート(日本企業は543社、米国企業は386社)から、DXの取り組み状況の経年変化や最新動向を掲載。DX推進における課題を抽出し、求められる取り組みの方向性を示唆している。また、IPAのなかに有識者委員会を設置して、現場の経営者に加えて、技術、IT人材に関する専門家による知見を盛り込み、有識者のコラムも掲載している。
新たな取り組みとして、154件の公開事例を分析し、日本のDXの状況を、俯瞰図を用いながら、「企業規模」、「産業」、「地域」の3つの軸で可視化。読者のニーズに応じてDX事例を探しやすくしている。「地域」別俯瞰図では、北海道では農業でのデジタル活用、甲信越ではドローンによる森林調査などが行われいること、東北や北陸、四国では働き手の減少や高齢化といった地域課題の解決へのデジタル活用が進展していることがわかったという。
DX白書 2023のなかから、注目される内容に触れてみたい。
DX白書 2023によると、日本でDXに取り組んでいる企業の割合は69.3%であり、前回調査の55.8%に比べると、この1年でDXに取り組む企業の割合は増加していることがわかる。だが、全社戦略に基づいてDXに取り組んでいる企業の割合は日本では54.2%であるのに対して、米国は68.1%と差が開いており、IPAでは、そこに日本のDXの課題があると指摘している。
-
日本でDXに取り組む企業の割合は増加しているが……
また、DXの取り組みが成果になっているとした日本の企業は58.0%と前回調査の49.5%から増加しているものの、米国では89.0%の企業が、成果が出ていると回答。DXの成果にも大きな差か出ていることが明らかになった。
成果を細分化すると、「アナログ・物理データのデジタル化」といったデジタイゼーション、「業務の効率化による生産性向上」といったデジタライゼーションに関しては、日米の企業で成果についての差は小さいが、「新規製品・サービスの創出」や「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」といったデジタルトランスフォーメーション(DX)では成果に対する差が大きく、ここでは、日本企業で成果が出ているとの回答は20%台であるのに対して、米国企業では7割前後にも達している。
-
DXの取り組みが成果になっているとした日本の企業。増えているとはいえ、米国との差は大きい
「DX白書 2023の副題に掲げた、『進み始めたデジタル、進まないトランスフォーメーション』といった状況を浮き彫りにしている。日本の企業のデジタル化は進んでいるものの、本質的な変革は進んでいない」と、日本企業における課題を提示した。
また、「ITに見識がある役員が3割以上いる」という企業は、日本では27.8%、米国では60.9%となり、2倍以上の差があることがわかったほか、経営者とIT部門、業務部門の協調ができている企業は、米国では80.1%であるのに対して、日本では37.1%に留まっていることもわかった。
「DXの推進は、経営がイニシアティブを執ることが大切であるが、日本ではITを理解した上で、経営の意思決定を行える環境が不十分である。また、経営層と部門との連携が弱く、DXを推進していく体制が十分ではないことも浮き彫りになった」としている。
-
ITに見識がある経営層が圧倒的に少ないという課題がある
DX推進プロセスの重要度と達成度についての調査からも興味深い結果が出ている。
日米企業を比較すると、米国では重要度と達成度がいずれも高い水準にあるのに対して、日本では重要度は高くても、達成度が低いという状況になっているからだ。
例えば、「全社員による危機意識の共有」では、日米企業ともに重要度は高いものの、達成度には大きな差がある。また、「自律性と柔軟性を許容するアジャイルな変革」、「目に見える成果の短いサイクルでの計測と評価」の項目は、日本では重要度も達成度も低い結果になっており、「DXの根幹である迅速性を捉えたこれらの項目において、重要度が低いことは、DX推進における日本の企業の大きな問題点だといえる」と述べた。
-
日本では重要度は高くても、達成度が低いという状況
IPAでは、DX戦略の推進においては、ビジョンの策定、取り組み領域の策定、推進プロセスの策定、成果評価とガバナンスという一連のプロセスを、なるべく早いサイクルで繰り返し、失敗から修正、学習しながら進めることが大切であるとし、さらに、ITシステムやIT人材、データなどのDXを下支えする経営リソースを戦略的に活用する必要性を強調している。
DX人材についても、日米の企業では大きな差が出ている。
米国企業では、DXを推進する人材の量については、「やや過剰」「過不足はない」と回答した企業が73.4%となっているのに対して、日本では、DXに取り組んでいると回答した企業に限定しても、「やや過剰」「過不足はない」としている企業は10.9%に留まっている。それに対して、「大幅に不足している」との回答は、米国では3.3%だが、日本では49.6%と半数近くになっており、DX人材に対する状況が大きく異なっていることがわかった。「日本ではやや不足していると回答した33.9%を加えると83.5%の企業が人材不足と回答している。前回調査に比べても、大幅に不足していると回答した企業が大きく増えている。DXへの取り組みが増加するのに従って、人材不足が目立ってきた」と分析した。
-
日本企業はDXを推進するための人材の確保にも苦戦している
また、DXを推進する人材像の設定状況を聞くと、日本では「設定していない」とする企業の割合が40.0%を占めており、米国ではわずか2.7%であることもわかった。
「日本の企業ではDX人材が足りないといっていながら、どういう人材が必要なのかが明確になっていない。DX人材の獲得、育成に向けた入口の部分が整備されておらず、それが適正な人材を確保できないことにつながり、人材不足が解消されないという課題を生んでいる」と警鐘を鳴らした。
-
DX人材の確保に苦戦する以前に、そもそも、「どういう人材が必要なのか?」が明確になっていない
さらに、「日本企業では外部からのDX人材の採用が難しく、社内でDX人材を育成することを重視している企業が多い。だが、人材育成のための施策がきちっと打てていないのも実態である」とし、「日米企業ともに、DX案件を通じたOJTプログラムで育成するという方法が最も多いが、プロジェクト数の違いもあり、OJTにつなげることができる数に差がある。日本ではOJTによる人材育成に会社として取り組んでいる企業は23.9%であるのに対して、米国では60.1%に達している。OJTだけでなく、リーダー研修、デジタル技術研修でも日本の企業は準備ができておらず、具体的な人材育成策が不十分である」と指摘した。
日本の企業におけるDXを推進する人材への育成予算については、「DXの成果がある」と回答した企業では「育成予算を増やした」という比率が42.8%となり、「DXの成果なし」と回答した企業の20.9%の約2倍になっている。育成予算の増減とDXの成果との間には相関が見られている。
また、DXを推進する人材の評価基準について、米国では63.8%が「基準がある」と回答したのに対して、日本では「基準がある」が12.0%となり、逆に「基準がない」が79.3%と約8割を占めている。
「日本の企業は、DX人材の獲得、育成の入口前段階の整備すらできていないともいえる。評価を整備しないと、獲得した人材や、育成した人材が外部に流出するリスクが高まる。評価の仕組みを整備することが急務である」と提言した。
技術の観点では、ビジネスニーズに対応できるITシステムに求められる機能に関して調査。ここでも、日米の企業で意識の差が出ている。
IPAの古明地部長は、「重要度という点では、日米の企業に大きな差がないものの、達成度では米国企業が、いずれの項目においても高い水準となっている。達成度において、日米で大きな差が出ている」としながら、「『変化に応じ、迅速かつ安全にITシステムを更新できる』という項目は、日本の企業のなかで最も重要度が高いものになっているが、達成度は米国企業に比べて、かなり低くなっている。DXに必要なスピードやアジリティの観点では改善が求められる」と指摘。さらに、「日本で達成度が高いのは『プライバシーの強化』と『場所に依存せず業務を遂行できるリモートワーク』であり、守りのIT投資であること、コロナ禍での対応といった部分に留まっている。DXの推進とは異なる部分での達成度が高いのが現状である」と語った。
-
日本でDX達成度が比較的高いな部分でも、中身はコロナ禍での対応など、守りのIT投資であり、DXの推進とは異なる部分での達成度が高いだけという現状
また、ITシステムの開発手法や技術については、ビジネス環境の変化に迅速に対応するために必要とされるマイクロサービスやコンテナの活用が、日本では1~2割の企業に留まっており、いずれも活用率が半数以上となっている米国企業との差が明らかになった。だが、パブリッククラウドやSaaSの利用は想定的に増加しているという。
レガシーシステムの状況については、「レガシーシステムが半分以上残っている」と米国企業は22.8%であるのに対して、日本企業は41.2%となっている。「日本企業におけるレガシー刷新は、かなり遅れている。これがDX推進の足かせになっているのではないか」と分析した。
-
相関から、日本企業におけるレガシー刷新の遅れが、DX推進の足かせになっているという指摘も
データの利活用については、「全社で利活用している」と「事業部門、部署ごとに利活用している」の合計値は、日本が55.0%、米国が52.3%と、日本がやや上回っている結果が出たが、米国企業では「顧客サービス」、「営業・マーケティング」、「製品・サービスの開発」、「製造工程・製造設備」、「コールセンター・問い合わせ対応」、「ロジスティック・調達・物流」、「サプライチェーン」において、いずれも6~8割の企業で効果が出ているのに対して、日本で効果があるとした割合は1~3割に留まっている。さらに、「成果を測定していない」とする日本企業は5割前後に達しており、「日本企業はまだデータ活用の基礎段階にある」と総括した。
また、「データの利活用に取り組む予定がない」とする企業が、米国の12.2%に対して、日本は20.5%と多く、「日本企業では、データ利活用の姿勢において二極化が進展している」とも指摘した。
-
全体の割合ではデータの利活用が進んでいるものの、推進の姿勢には二極化の傾向
さらにAIの利活用については、日本企業のAI導入率が22.2%であるのに対して、米国企業では40.4%に達していることを示しながら、「前回調査では、日本企業におけるAI利用率が一気に上昇したが、今回の調査では微増に留まっている。社内におけるAIへの理解が不足していることや、AI人材が不足していることが、導入の進展を阻む要素になっている」とした。
-
AIの利活用では、理解不足と人材不足の課題がより深刻だ
ちなみに、IPAでは、DXを実現するためのあるべきITシステムの要件として、ITシステムとその開発運用の体制が、変化に対して俊敏かつ柔軟に対応できる「スピード・アジリティ」を持っていること、社内外の円滑かつ効率的なシステム間連携を目指す「社会最適」であること、データ活用を中心に据えて社内外へ新たな価値を生み出していく「データ活用」の3点をあげ、「IPAでは、DX実践手引書ITシステム構築編のなかで、これらの要素を示している。DXの進展には、この3点を取り込めるITシステムになっていることが大切である」とした。
今回の「DX白書 2023」は、副題に示されたように、日本企業におけるデジタル化が進展していることは明らかになったものの、トランスフォーメーションが進まず、DXの成果を刈り取れていないことも浮き彫りになった。それは日米企業のあらゆる項目からの比較で、より明白になったといえる。
DXに重要なのは、D(デジタル)ではなく、X(トランスフォーメーション)である。日本の取り組みが、DXにまで至っていないことが示された内容だったといえるだろう。
なお、「DX白書 2023」は、IPAのウェブサイトで、PDF版をダウンロードできる。PDF版は377ページで構成されている。また、要点を37ページにまとめた「エグゼクティブサマリー」を同時に公開し、経営層にも理解しやすくしている。さらに、3月に刊行予定の書籍版では、付録として、日本、米国、欧州、中国におけるデジタル関連制度政策を概観した「【制度政策】制度政策動向」を加えるという。3月23日には、一般向けの解説セミナーをオンラインで開催する予定だ。